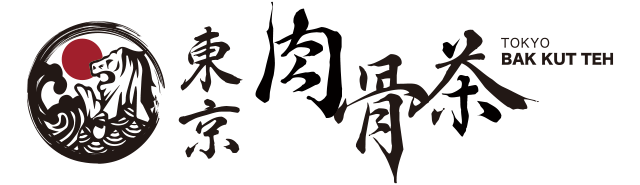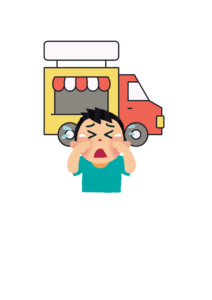皆さん、こんにちは。「東京肉骨茶(とうきょうバクテー)」の伊藤です。
キッチンカーでの独立を夢見ている皆さんに、私の経験が少しでもヒントになればと思い、私たちの看板メニューである「肉骨茶」についてのお話をしています。 今回は、お客様の声の大切さについてです。
東京肉骨茶の原点はシンガポールのソウルフード
私が肉骨茶(バクテー)と出会ったのは、シンガポールに8年ほど駐在していた頃です。
現地の言葉で「バク」は肉、「テー」は茶を意味するこの料理は、豚の骨付き肉をニンニクや漢方、胡椒などと一緒に煮込んだスープで、まさにシンガポールのソウルフード。
街の至る所に専門店があり、私はすっかりその魅力に取り憑かれ、中でもお気に入りで通いつめたお店の店主に頼み込んで、レシピを教わりました。
しかし、いざ自宅のキッチンで作ってみると、あのお店の味には到底及びません。
理由は明白でした。
大きな寸胴で大量の肉を長時間煮込むからこそ、あの奥深い味が出るのです。
家庭の鍋では再現が難しく、私は家で再現することを諦め、お店に通い続けました。
「本場の味」は、日本では通用しなかった
サラリーマン生活に終止符を打ち、コロナ禍でテイクアウト需要が高まる中、私はキッチンカーで肉骨茶をやることを決意しました。
プロ用の大きな寸胴とバーナーを揃え、教わったレシピで仕込むと、驚くほど美味しいスープができました。
「これならいける!」と自信満々で丸の内のオフィス街へ。
しかし、現実は厳しいものでした。
そもそも、お客様の7〜8割は「バクテー」という料理を知らないのです。
そして、私が直面した最大の壁は、お客様が「アジアンフード」に抱くイメージとのギャップでした。
「なんか辛い味付けないの?」
「アジアンフードだから、もっとピリ辛だと思ってた」
何人ものお客様から同じような声が寄せられました。
私にとって肉骨茶は、胡椒は効いていても、唐辛子系の辛さとは無縁の、滋味深い優しいスープ。
しかし、食べたことのない方々にとっては「アジアの料理=スパイシー」というイメージが強かったのです。
「本場はこうなんです」と説明したところで、お客様の「期待」とのズレは埋まりませんでした。
お客様の声が「正解」を教えてくれた
この経験は、私にとって大きな転機となりました。
「本場の味をそのまま提供すること」が、必ずしもその土地に受け入れられる「正解」ではないと痛感したのです。
そこで、ある試みをしました。
シンガポールではまず見かけませんが、お好みで辛さを足せるように、小さな容器に「豆板醤」を添えてみたのです。
すると、これが大ヒット。今では、丸の内の常連さんの半分以上が「豆板醤つけてください」と言うほど、定番のトッピングになりました。
さらに、日本人の味覚の根底にある「出汁」の文化にも着目しました。
日本では、肉骨茶を食べたことがない人がほとんどです。本場のレシピにはない「和の出汁」を加えることで、なじみのある味と受け取ってもらえるのではないか。
出汁の味を、肉骨茶の風味を壊さずに融合させる。これは非常に難しい挑戦で、完成までには長い時間がかかりましたが、この改良によって、より多くの日本人のお客様に「美味しい」と言ってもらえるようになりました。
お客様の意見が割れたときは・・・
面白いことに、シンガポールに長く住んでいた経験のある方が食べに来てくれることもあります。
彼らの反応は、正直に言うと真っ二つ。
「これはこれで美味しいね」と言ってリピーターになってくれる方が半分。
そして「やっぱりシンガポールで食べた味とは違うね」と、それきりになってしまう方が半分。
どちらの声も貴重ですが、私はビジネスとして、お客様の圧倒的多数である「日本で初めて肉骨茶を食べるお客様」に喜んでもらうことを選びました。
私の料理は「シンガポール本場の味の再現」ではなく、日本のお客様に愛される「東京肉骨茶」なのだと覚悟を決めた瞬間でした。
守るべき核と、進化し続ける勇気
もちろん、何でもお客様の言う通りに変えれば良いというわけではありません。
私の中には、肉骨茶として譲れない「核」があります。
それは「豚肉とニンニク」です。
豚肉に含まれるビタミンB1は、ニンニクに含まれるアリシンと結合すると、体内への吸収率と持続力が高まります。この最強の組み合わせこそが、肉骨茶の根幹です。
また、肉の部位にもこだわりました。
シンガポールでは豚の様々な部位が入っていますが、日本では手に入りにくいものも多い。そこで試行錯誤の末、食感も良く、バックリブをメインにしつつ、出汁も出る「バラ先軟骨」も入れることにしました。
これも「東京肉骨茶」独自の工夫です。
そして、味の進化はお客様との対話から、今も生まれ続けています。
ある常連さんが「刻んだ青唐辛子(グリーンチリ)を入れたら美味しかったよ」と教えてくれたのがきっかけで、味変のトッピングとして提供するようになりました。これも大好評です。
これからキッチンカーを始める皆さん。
自分の作りたい味、自分のレシピを持つことはもちろん大切です。
しかし、それ以上に大切なのは、お客様の声に真摯に耳を傾け、対話をしながら自分の料理を柔軟に進化させていく勇気です。
私の肉骨茶は、私一人で作ったものではありません。
キッチンカーのカウンター越しに交わした、たくさんのお客様との会話の中から生まれてきたものです。
あなたの料理も、きっとお客様との出会いの中で、唯一無二の看板メニューへと育っていくはずです。応援しています!