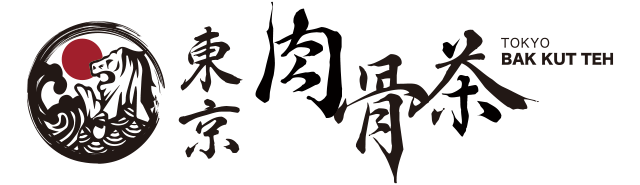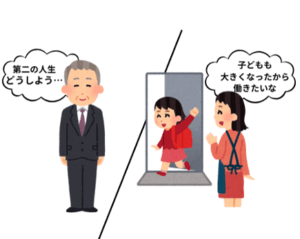皆さん、こんにちは。「東京肉骨茶」(とうきょうばくてー)の伊藤です。
私たちがキッチンカーでバクテーを販売していると、お客様から「“肉骨茶”って、なんて読むんですか?」「どういう料理なんですか?」と、本当によく聞かれます。
この連載では、キッチンカーでの独立・開業を目指す皆さんを応援しているわけですが、もしかしたら皆さんの中にも、まだ「肉骨茶」に馴染みのない方がいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、私たちが惚れ込み、商材として選んだこの料理=「肉骨茶(バクテー)」の基本の「キ」からご紹介したいと思います。
肉骨茶(バクテー)とは?
「肉骨茶」と書いて「バクテー」と読みます。 これは、豚のスペアリブを、ニンニクや胡椒、漢方食材と一緒にじっくり煮込んだ薬膳スープです。
長時間煮込むことで、豚骨からコラーゲンやミネラルがスープに溶け出し、滋養強壮の効果があるとされ、古くから現地の人々に愛されてきました。
「肉・骨・茶」・・・名前の由来は?
この「肉骨茶」の「茶」という漢字を見て、「スープにお茶が入っているの?」と疑問に思う方が非常に多いです。
「肉」と「骨」は、その名の通り、メインの食材である「豚のスペアリブ(肉)と骨」を指します。
では「茶」は何か。これは、スープにお茶の葉が使われているわけではありません。
この料理は、もともと脂の多い豚肉を食べる際に、中国茶(飲茶)を一緒に飲みながら楽しむのが伝統的なスタイルでした。
脂っこい食事をすっきりと締めるための、先人の知恵ですね。 この「お茶と一緒に楽しむ食文化」そのものが、料理の名前の一部として定着した、というのが名前の由来として広く知られています。
ルーツと二大スタイル(シンガポール vs マレーシア)
バクテーのルーツは、もともと中国南部(福建省や広東省)にあると言われています。 それがシンガポールやマレーシアへ移住した華人労働者によって持ち込まれ、港で働く人々の朝食として提供されるようになりました。
一日のハードな仕事に必要なエネルギーを補給し、疲れた体を癒やすための「スタミナ料理」。それがバクテーの原点です。
そして、このバクテーは、主にシンガポールとマレーシアで独自の発展を遂げ、現在では大きく分けて二つのスタイルがあります。
- シンガポール風(白バクテー)
透き通ったクリアスープが特徴。胡椒とニンニクがガツンと効いた、スパイシーな味わいです。 私たち「東京肉骨茶」が提供しているのは、このシンガポール風です。
- マレーシア風(黒バクテー)
中国醤油(ダークソイソース)を使った黒いスープが特徴。漢方食材の香りが豊かで、野菜やキノコなど具だくさんなスタイルが多いです。
なぜ今、肉骨茶が魅力的なのか
バクテーは、単なる「美味しいスープ」ではありません。
胡椒やニンニクは体を温め、免疫力を高める効果が期待できるとされ、風邪予防や疲労回復にも良いと言われています。
つまり、「薬膳」の要素を含んだ「日常的な健康食」としての側面が非常に強いのです。
シンガポールでは、今でも朝食として親しまれていたり、家族や友人が集まる食卓の中心にあったりと、シンガポールのソウルフードとして人々の生活に深く根付いています。
バクテーは、かつて港湾労働者の体を支えたように、現代を忙しく生きる日本の皆さんにも活力と健康を届けられる、ポテンシャルの高いメニュ
ーだと私は思っています。
東京肉骨茶は、日本人に合うように味をアレンジしていますが、皆さんも現地に行った折には、ぜひ本場の味も試してみてください!